| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※初診の方の受付は19時まで
\ お電話はこちらから /
0422-38-8708
\ 24時間予約受付中 /
\ 当日予約OK! /
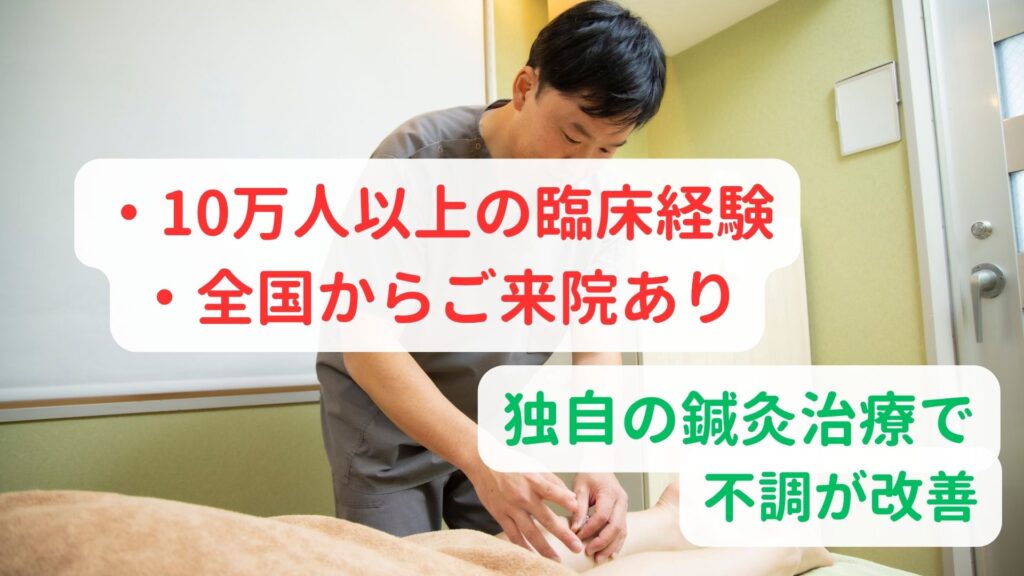
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

「喉のつかえやげっぷが楽になる方法がわからない」
「胸焼けのような不快感の治し方やツボを知りたい」
「自律神経が疲れるとげっぷが頻繁に起こる」
このような症状でお悩みの方はおられないでしょうか。
この不調は西洋医学では逆流性食道炎の特有な症状と合わせて起こりやすいため「逆流性食道炎」と診断されることがあります。
しかし、逆流性食道炎がなくても「げっぷ、喉のつかえ感のみの症状」だけが頻繁に起こることがあり診断されないことがあります。
そのため内科では「逆流性食道炎と診断がつかずにはっきりした治療を受けられない」という問題が起きてしまい、結果として不調で悩む患者様は処方された薬を漫然と服用し症状が治らずに悪化することも多々あります。
今回は「止まらないげっぷは東洋医学で改善できる」と題して東洋医学的な観点でこの症状の原因と改善方法を解説していきます。
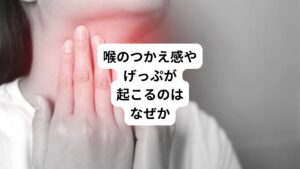
喉のつかえ感やゲップが出るのはなぜでしょうか。
一般的に「喉のつまり感やげっぷはストレスが原因である」とか「自律神経が乱れてげっぷが出る」と答えられる方はいるかと思います。
しかし「なぜストレスが胃に不調をきたしつかえ感、ゲップが出るのか」というメカニズムまで答えられる方は少ないかと思います 。
この部分に悪化を防ぐための根本的な治療が秘められています。※1
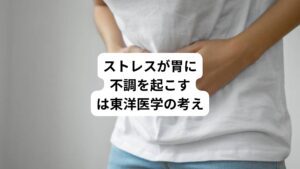
東洋医学では気血の巡りを調整しているのが「肝(かん)」の役割と考えています。
現代医学では肝は自律神経の調整と血液の貯蔵と説明できます。
その中でストレスは肝に影響を与え、肝が調整している気血の巡りを滞らせます。
これを東洋医学では「気滞 きたい」と呼びます。
この気滞という状態は身体のどの部分でも起きますが、とくに起きやすいのが喉になります。
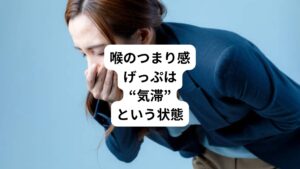
東洋医学では気血が淀みなくスムーズに流れている状態を健康と考えます。
この気血が滞ると不調が起きます。
喉のつかえ感やげっぷの症状は胸部と喉を通るこの気の巡りが滞ることで起こります。
しかし、この症状は逆流性食道炎のみに起こる症状ではなく、肝の気が喉で滞ればどのような病気であっても起こると考えます。
肝の気の巡りが滞ることで起こるこれらの症状からどのように症状が進行するかはその人の体質次第といえます。
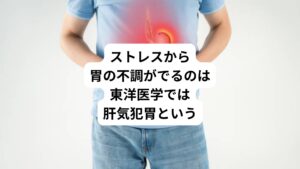
では、喉のつかえ感やげっぷから胃に不調が起こる病態を東洋医学ではどのように説明しているのでしょうか。
それを東洋医学の専門用語で「肝気犯胃 かんきはんい」と呼びます。
メカニズムとしては肝の気の巡りが滞り鬱滞が起こるとその鬱滞が胃に流れ込み胃の調子を狂わすというものです。
西洋医学では「ストレスにより交感神経が高まり胃酸の分泌が増えて胸やけを起こす」など自律神経の乱れによって説明しますが、東洋医学では気の巡りと臓腑(ここでは肝と胃の関係)で説明するのが特徴です。
逆流性食道炎は東洋医学ではこの肝気犯胃という状態をさします。
そのため喉のつかえやげっぷを改善させるためには東洋医学に基づく治療でこの肝気犯胃を解消させることが重要です。
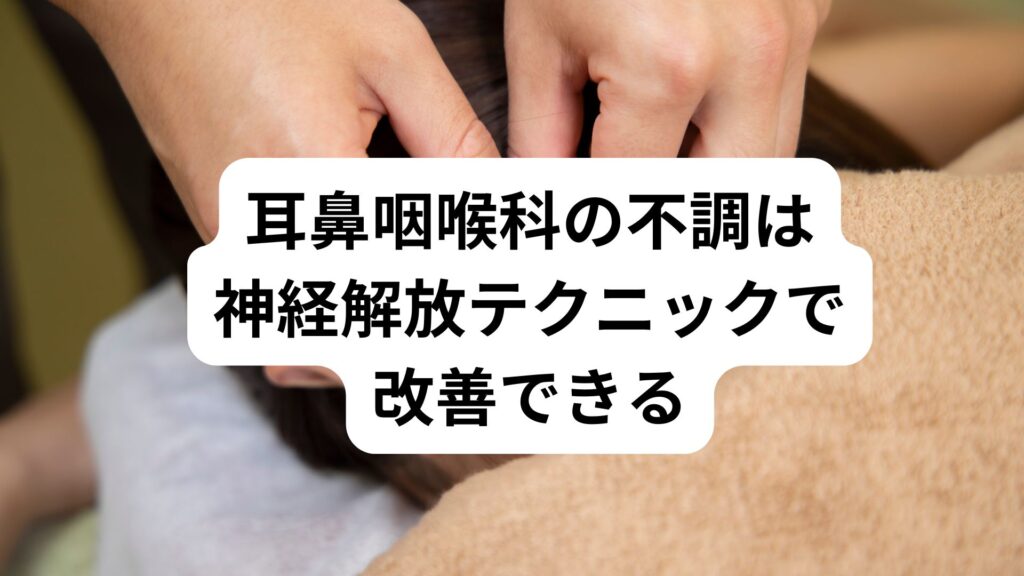
東洋医学は西洋医学とは違って「逆流性食道炎」という病気の治療はありません。
不調が起きている体質(症状や病態)から根本的な原因を見つけて治療方法を組み立てます。
今回は気滞と肝気犯胃という不調がこれに当たります。
当院でもこの考えに則って東洋医学の鍼灸治療を行います。
気血の巡りをスムーズにし、肝と胃の不調を改善させて喉のつかえ感やげっぷを完治させます。
「どこに行けば自分の不調を正しく改善できるかわからない」と治療方法でお悩みの方は当院にお気軽にご相談ください。
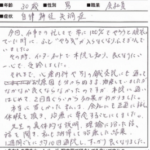
実際に当院ご来院になって改善された患者様の声と改善までの経過を報告します。
同じようにつらい思いをされている方の役に立てるのならばと皆さん快く掲載を許可頂きました。
これを読まれている患者様のご参考になれば嬉しく思います。
下記のリンクから別ページでご覧ください。
